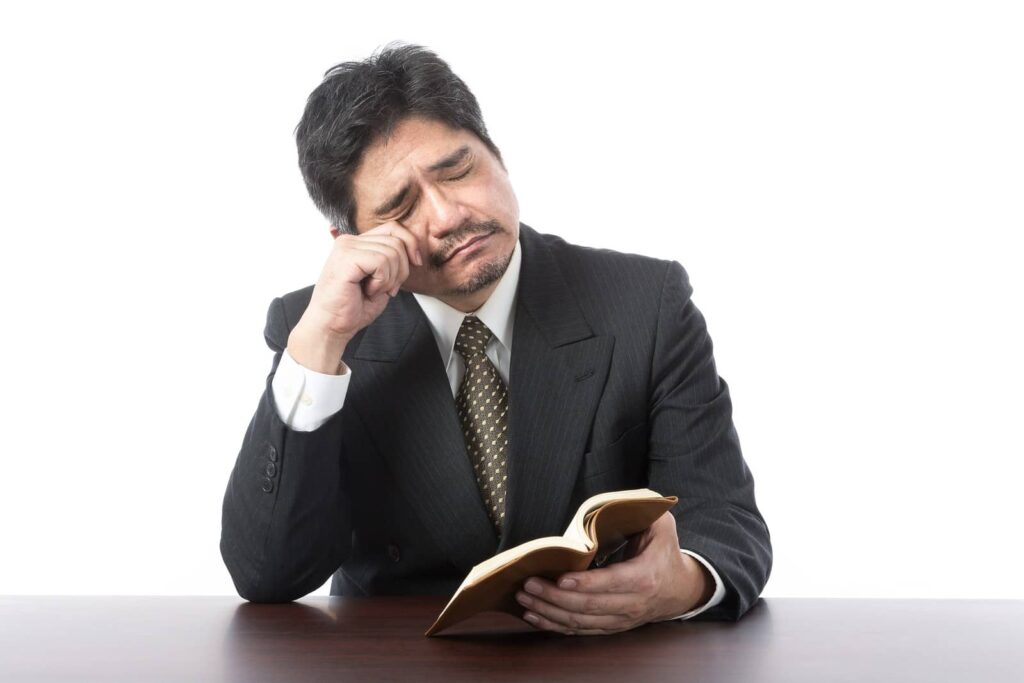「借金滞納で年金まで差し押さえを受ける?」
「年金が差し押さえられたら困る……」
「どうにかして差し押さえを防ぎたい!」
こんな悩みを抱えていないでしょうか?
借金を滞納し続けていると、最終的には差し押さえを受けてしまいます。
もし年金まで差し押さえられると、今後の生活に困ってしまうでしょう。
結論からお伝えすると、借金が原因で年金が差し押さえられることは基本的にありません。
また、借金が自力で返済できなかったとしても、差し押さえを防ぐ方法はあります。
この記事では、年金が差し押さえられないか心配な人に向けて、以下の内容をまとめました。
- 年金が差し押さえられるケース
- 差し押さえを防ぐための方法
- 差し押さえられた年金を取り戻す方法
この記事を読めば、借金で絶望している人も解決方法が見つかります。
自力で返済できない借金を負っている人は、差し押さえ回避のために最後まで読むことをおすすめします。
Contents
年金は差し押さえ禁止財産

借金を滞納しても、年金が差し押さえられることは基本的にありません。
国民年金や厚生年金は生活を営むために必要な財産で、「差押禁止財産」として定められているからです。
例えば、借金を滞納して家や車などの財産が差し押さえられたとしても、年金は差し押さえを受けずに済みます。
年金は特別なケースを除いて差し押さえられない、と覚えておきましょう。
年金が差し押さえられるのはどのようなケースか

先ほど説明した通り、年金は基本的に差し押さえを受けません。
しかし、場合によっては差し押さえを受けてしまうケースもあるので、しっかり確認しておきましょう。
年金が差し押さえられるのは、以下のようなケースです。
- 年金担保貸付を受けている場合
- 公租公課を納めなかった場合
- 年金の振り込み後に差し押さえを受けた場合
それぞれ順番に解説します。
年金担保貸付を受けている場合
年金担保貸付を受けている場合は、年金の差し押さえが認められます。
- 独立行政法人福祉医療機構が行っている「年金担保貸付」
- 日本政策金融公庫が行っている「恩給・共済年金担保融資」
上記の融資を受けている場合、借金を返済するために年金から天引きが行われます。
公租公課を納めないことによる滞納処分を受けた場合
滞納処分を受けた場合にも、年金は差し押さえられます。
滞納処分はいわゆる租税公課を滞納したときの強制徴収のことで、滞納処分が実施される例は次のとおりです。
- 地方税
- 下水道受益者負担金
- 道路占用料
- 土地区画整理事業の清算金
- 保育所保育費用
- 河川占用料
- 分担金
- 加入金
- 過料(行政罰の罰金)
租税公課を滞納した場合は、通常の借金の滞納よりも差し押さえは早くなります。
また、全額差し押さえられるわけではなく、年金受給額から一定額を引いた額から差し押さえられます。
年金の振り込み後に差し押さえを受けた場合
年金貸付担保や、滞納処分以外にも借金が原因の差し押さえを受けることがあるので注意が必要です。
年金は銀行に振り込まれたあと、預金債権として扱われます。
つまり、年金が振り込まれたあとの差し押さえには制限がなく、年金支給日を狙って差し押さえられる可能性があるということです。
生活保護費の場合も、同様の方法で差し押さえられてしまうことがあります。
しかし、年金は「生活維持に必要な収入」として保護されるべきであり、上記のような差し押さえは法律の抜け穴をついたやり方だといえるでしょう。
滞納処分を回避するための方法

税金や社会保険料には、負担の減免を認めてくれる制度があります。
どうしても生活が苦しい場合は、早めに減免の手続きを申し立てることで租税公課の滞納を防ぐことができるのです。
救済制度には以下の4つがあります。
- 住民税の免状を申請する
- 年金保険の減免・猶予を申請する
- 国民健康保険の減免制度を活用する
- 減免を受けられないときは分納協議で対応
税金等の支払いが難しい人は、必ず確認しておきましょう。
住民税の免状を申請する
下記に該当するような人は、住民税の負担を軽減してもらえます。
- 生活保護を受けている
- 障害者・未成年者・寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の場合であれば年収204万4000円未満)の場合
- 前年中の合計所得金額が市区町村の条例で定める額よりも低い場合
寡婦(かふ)とは、配偶者と離別して再婚していない人を指します。
住民税の減免は原則「納期限前の申告」が必要となり、滞納したあとの免除は認められないので注意しましょう。
年金保険の減免・猶予を申請する
年金保険料は、前年度の所得額に応じて減免や猶予を受けられます。
減免の基準については以下のとおりです。
| 減免の程度 | 適用基準となる前年所得額 |
|---|---|
| 全額免除 | 「(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円」よりも低い場合 |
| 3/4免除 | 「78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」以下の場合 |
| 半額免除 | 「118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」以下の場合 |
| 1/4免除 | 「158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」以下の場合 |
| 支払い猶予 | 「(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円」以下の場合 |
国民年金保険の減免は、25ヶ月前までならさかのぼって適用してもらえます。
国民健康保険の減免制度を活用する
国民健康保険も減免してもらうことが可能です。
前年度の所得が低いとき、災害などの不測の事態にあったとき、そして生活が困窮しているときは減免、または全額免除を認めてもらえることがあります。
国民健康保険の減免制度は、地域によって細かく違うので注意が必要です。
また、申請には期限があるので遅れないようにしましょう。
減免を受けられないときは分納協議で対応
租税公課を滞納しそうな場合は、滞納分の分割払いが可能です。
租税公課の分納は、財産隠しなどの悪質な支払い逃れをしない限りは、ほとんどのケースで応じてもらえます。
ただし、分納期間にはある程度の制約があるので注意が必要です(一般的には3〜6ヶ月程)。
申請期限を過ぎてしまったり、条件に適合しなかったりして減免を受けられない場合は、分納協議を利用するのが良いでしょう。
差し押さえを防ぐには「債務整理」が有効
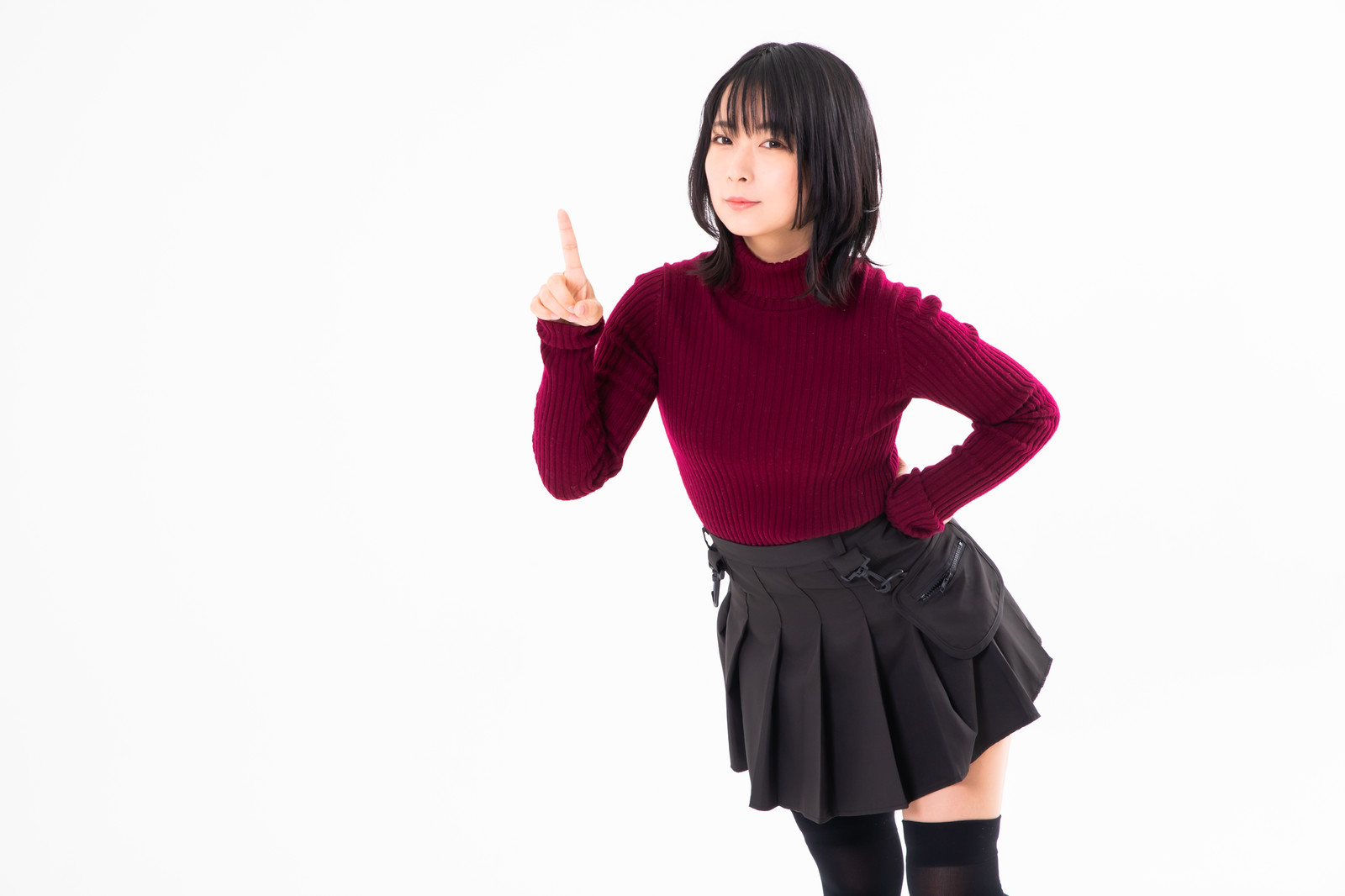
差し押さえを防ぐ方法としては、債務整理をするのが良いでしょう。
債務整理のメリットは以下の3つです。
- 金融機関からの取立てが完全にストップする
- 借金の返済を一時的にストップさせられる
- 差し押さえを取り消させることができる
弁護士・司法書士に債務整理を依頼すれば、取り立て・返済はストップします。
返済が一時的になくなれば、租税公課への対応が可能になり、借金の不安からも解放されるでしょう。
債務整理を行えば差し押さえの取り消し・中止も可能です。
例えば、年金を差し押さえられたあとに自己破産を申し立てれば、破産管財人によって差し押さえを停止させられます。
また、債務整理を行っても債権者から訴訟を起こされる可能性はありますが、弁護士・司法書士に依頼していれば対応してもらえます。
関連記事⇒受任通知と債務整理の関係?支払いや督促が止まる流れとメリット
差し押さえられた年金を取り戻す方法は?ケースごとに解説

実は、すでに差し押さえられてしまった年金を取り戻すことも可能です。
以下のケースごとに、 それぞれ年金を取り戻す方法を見ていきましょう。
- 滞納処分をされた場合
- 預金から差し押さえられた場合
- 民間の金融機関に差し押さえられた場合
滞納処分をされた場合
滞納処分の場合は、年金を取り戻すのはかなり難しいでしょう。
年金受給権の差し押さえを解除するには、次のいずれかを満たす必要があります。
- 納付、充当、更正の取消などにより滞納を解消させる
- 滞納分の一部を納付することで「超過差し押さえ」の状態にする
- 年金以外の差し押さえ可能な財産を徴収機関に差し入れる
現実的に考えると、差し押さえ解除には滞納している租税公課を納付するほかありません。
下の2つの「超過差し押さえの状態にする」や、「差し押さえ可能な財産の差し入れは」金銭的に難しいでしょう。
預金から差し押さえられた場合
銀行預金から差し押さえられた場合、返還を求めることも可能です。
年金には差し押さえ額の制限があり、それを超えて差し押さえられた部分に関しては返還を求めることもできます。
実際に、差し押さえ額に問題があるとして異議を述べたことで、返金されたケースは少なくありません。
年金が銀行預金から差し押さえられたら、返還を求めた方が良いでしょう。
まとめ
年金の差し押さえが心配な人は、債務整理がおすすめです。
年金は基本的に「差押禁止財産」ですが、以下のようなケースでは差し押さえられてしまう可能性があります。
- 年金担保貸付を受けている
- 公租公課を納めないことによる滞納処分
- 年金が振り込まれたあと差し押さえられる
債務整理を依頼すれば借金の取り立て・返済は止まりますし、年金の差し押さえをストップさせられる場合もあります。
借金は放置すればするほど深刻になります。
借金から目を背けて差し押さえのリスクを負っている人も、弁護士・司法書士に相談することで間違いなく状況は良くなるでしょう。