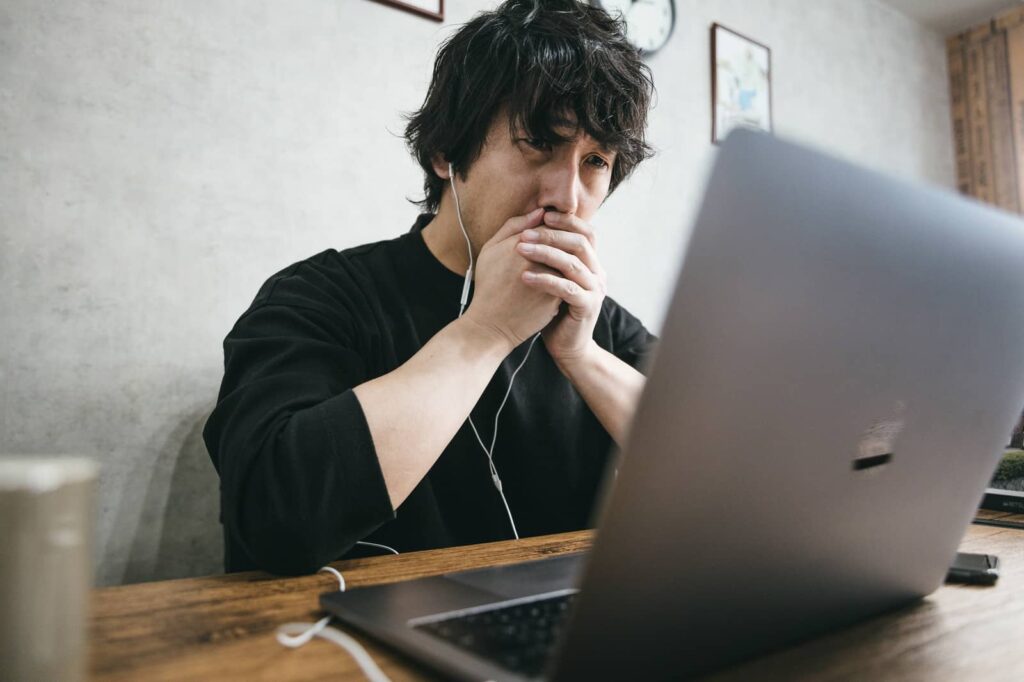「奨学金の保証人になるための条件は?」
「債務整理して保証人になれなくても、奨学金を借りる方法はある?」
こんな疑問を抱えていませんか?
奨学金を借りるには保証人が必要です。しかし、過去に債務整理を行っていて、子供の奨学金の保証人になれないのではないかと心配な人も多いと思います。
そこでこの記事では、奨学金の保証人について詳しくまとめました。
- 奨学金の保証人になる条件
- 保証人・連帯保証人の違い
- 保証人になれないときの対処法
さらに、保証人になれなかったときの対処法についても解説しているので、ぜひご覧ください。
Contents
奨学金の連帯保証人・保証人になる条件

奨学金とはいえ、借金は借金。
借り入れの際には、必ず保証人と連帯保証人が必要です。もし奨学者が返済できなくなった場合、保証人か連帯保証人が返済する義務があります。
連帯保証人・保証人になる条件について、順番に見ていきましょう。
連帯保証人になる条件
連帯保証人とは、学生と連帯して借金を返済する人です。
連帯保証人になる条件は、次の通りです。
- 奨学生が未成年の場合、親権者か未成年後見人
- 奨学生が成年者の場合は、4親等以内の親族
- 未成年や学生でないこと
- 奨学生本人の配偶者でないこと
- 自己破産や任意整理など、債務整理中でないこと
- 60歳未満であること
上記以外にも、安定した収入や資産があるかどうかもみられます。
連帯保証人は、基本的に両親でなければいけません。もし両親がいない場合、4親等以内の親族(祖父母や叔父、叔母など)でも大丈夫です。
保証人になる条件
保証人とは、債務者や連帯保証人が返済できなくなったとき、代わりに返済を行う人です。
保証人は連帯保証人以外の人(つまり両親以外)である必要があるため、両親以外の4親等以内の親族が対象になります。
また、学生やその両親と家計を別にしている人でなければ認められません。
その他の条件は、基本的に連帯保証人と同じです。
連帯保証人・保証人の違い

連帯保証人・保証人は、似ているようで全く異なります。
違いを知らないまま連帯保証人・保証人になり、後で後悔する事例は非常に多いので注意しましょう。
連帯保証人・保証人の大きな違いは、以下の通りです。
- 保証人には3つの権利が認められる
- 連帯保証人は問答無用で支払いに応じる必要がある
つまり、保証人よりさらに重大な責務を負うのが連帯保証人と言えます。
それぞれ順番に解説していきます。
保証人には3つの権利が認められる
保証人は、連帯保証人と異なり以下の3つの権利が認められます。
- 催告の抗弁権
- 検索の抗弁権
- 分別の利益
「催告の抗弁権」は、支払いを催促されても債務者に請求するよう主張できる権利です。
「検索の抗弁権」では、債務者の支払い能力を証明できれば、先にそちらに請求・差し押さえするように主張することができます。
「分別の利益」とは、保証人が複数人いた場合に、それぞれで分けた金額を返済する権利です。
奨学金の場合、保証人と連帯保証人の2人がいるため、保証人が返済しなければいけない金額は全体の半分だけです。
保証人は、連帯保証人と違って請求を求められても抗うことができます。
連帯保証人は問答無用で支払いに応じる必要がある
連帯保証人は、前述の3つの権利が認められません。
つまり、返済を求められると問答無用で支払いに応じる必要があるのです。
例えば、債務者(奨学生)に返済能力がある場合でも、返済を請求された場合は拒むことができず、債務の全額を支払う必要があります。
保証人と連帯保証人では責任が大きく違うので、必ず覚えておきましょう。
債務整理すると奨学金の保証人になれない

残念ながら、債務整理していると奨学金の保証人になれません。
債務整理すると信用情報機関に「事故情報」が登録され、保証人になれなくなります。
事故情報が登録される期間は、債務整理方法や信用情報機関によって異なります。
| 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
| JICC | 5年 | 5年 | 5年 |
| CIC | 5年 | 5年 | 5年 |
| KSC | 5年 | 10年 | 10年 |
例えば、奨学金を貸し出している日本学生支援機構は、KSCを参照しています。
つまり、任意整理を行った場合は完済から約5年、個人再生や自己破産の場合は約10年経つまで、奨学金の保証人になることはできません。
奨学金の保証人になれないときの対処法

保証人になれないからといって、即座に諦める必要はありません。
親が債務整理している場合でも、以下の3つの方法によって奨学金を借りることができます。
- 保証人候補の事故情報が消去されるまで待つ
- 別の親族に保証人になってもらう
- 期間保証制度を利用する
それぞれ順番に見ていきましょう。
保証人候補の事故情報が消去されるまで待つ
奨学金を借りる方法の1つ目は、保証人候補の事故情報が解除されるまで待つことです。
前述の通り、債務整理後に事故情報が登録されるのは一定期間なので、その期間が過ぎれば債務整理済みでも普通に保証人になれる可能性があります。
なお、事故情報が登録される期間は「完済後」から数え始めます。
例えば、個人再生を行ってその3年後に完済すると、実質的に13年間保証人になれないということになります。
また、事故情報が消えていても収入が不安定、または十分な資産がないと判断された場合は、普通に審査に落ちてしまうので注意しましょう。
別の親族に保証人になってもらう
奨学金を借りる方法の2つ目は、別の親族に保証人になってもらうことです。
親のどちらかが債務整理していても、その配偶者であれば審査に通る可能性があります。
また、それ以外でも兄弟や叔父、叔母など4親等以内の親族であれば、奨学金の保証人になることができます。
どうしても保証人になれない場合は、親族に依頼するのも一つの手でしょう。
機関保証制度を利用する
奨学金を借りる方法の3つ目は、機関保証制度です。
保証人になってくれる人がいなくても、機関保証制度を利用すれば、奨学金を支給してもらうことができます。
ただし、機関保証を利用すると、毎月3,000円ほど保証料がかかる点に注意です。
例えば、奨学金を5年かけて返済するなら3,000円 × 12ヶ月 × 5年 = 180,000円の保証料を余分に支払う計算になります。
まずは親族に保証人になってくれるよう依頼し、それでもダメなら機関保証を利用するのが良いでしょう。
まとめ
奨学金の借り入れには、保証人・連帯保証人が必要です。
保証人は、基本的に両親がなるものです。しかし、もし両親が債務整理していて保証人になれない場合でも、次の方法で借り入れることができます。
- ブラックリスト解除まで待つ
- 別の親族に保証人になってもらう
- 期間保証制度を利用する
借金を抱えている人は、債務整理で解決するのが賢明です。
保証人になれなくなるからといって、債務整理せずにやり過ごそうとすると、さらに厳しい状況に追い込まれてしまいます。
自力で借金を返済できないなら、1日でも早く弁護士・司法書士に相談して債務整理を行いましょう。